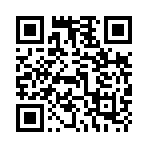前回に引き続き、「糖度計」の小話をいたしましょう!
こんな、ハンディータイプの「糖度計」(屈折計)もあるんですよ。。。メーカーは、日本の「アタゴ」社製。
スーパーマーケットの果物売場で、りんごの脇に「糖度13度以上」といった説明書きが添えられているのを見たことはないでしょうか。そうした果物の“甘さ”(=糖度)を測るのに使われているのが屈折計。アタゴは屈折計の国内シェアで約80%、世界でも154カ国以上で使用され、世界シェア約30%を誇るトップ企業です。 (株式会社 アタゴより)
接眼部からのぞくと、こんな感じ。。。目盛り部が見て取れます。
先端の採光板を開け、プリズム面に数滴、コンコードの果汁を垂らします。採光板を閉じ、再び接岸部から覗くと。。。
青と白の境界線が出来ていますね! 境の値の%(度)を読み取ります。
原理の仕組みを、「株式会社 アタゴ」ホームページより抜粋しましたので、ご参考までにお読みください。
水の入ったコップにストローを挿すと、ストローが曲がっているように見える。これが「光の屈折」という現象。屈折計はこの現象を利用して糖度・濃度を計測する。
光が進む速度は、真空中と大気中とでわずかに異なり、大気中と水中とを比べると速度差はもっと大きくなる。
5人が手をつないで同じ速度で走っている姿を想像してみよう。走りやすい運動場を走っている分には同じ速度だが、途中に砂場があったとする。右端のAさんから斜めに砂場へ入っていく場合、Aさんから順にBさん、Cさんと砂場に入り、走る速さは遅くなる。一方、左端のEさんは最後まで速さが変わらないので、Eさんが少し余分に距離を走れることになる。5人は手をつないでいるのでAさんとEさんの進める距離の差分だけ弧を描くような形になり、5人が向かう方向が少しずれることになる。
光の屈折を簡単に説明すると、おおよそこのような現象だ。先ほどの砂場の例を続けると、砂場(=水)にたくさんの石(=砂糖など)が混ざっていると、Aさんの走る速度はもっと遅くなり、Eさんとの差はさらに広がってしまう。そして5人が向かう方向の角度のずれ(=屈折率)もより大きくなるわけだ。
こうして生じる屈折率のわずかな違いに着目して、水に混ざっている砂糖などの割合(=糖度・濃度)を割り出すのが屈折計の仕組みだ。
この日、作業中でしたが、私宛で来客がありました。 台湾からのお客様です。
セラーの見学の他に、テイスティングもしていただきましたが、生ぶどうの集荷作業は滅多にないタイミングでしたので、上記の「糖度」を測る作業を実際にしていただきました。 日本のワインに大変興味のあるお客様でしたので、「信州ワイン」を最大限にPRさせていただきましたが、ワインを通じての、良好な「日台関係」がますます築けるとイイですね!
営業企画 橋詰