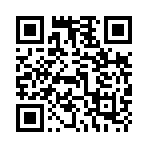信濃ワイナリー2F 通称「ワイナリーホール」には、とある一枚の油絵が展示されています。
縦90.9センチ 横116.7センチ F50号サイズの大きな油絵でして、「無題」ではありますが、弊社従業員の作業風景を切り取った大作でもあります。
ワイナリーフェスタの際にご覧になられた方も多いかと思われますが、この油絵。。。
さて、どんな秘密が隠されているのでしょうか?
『職場で死ねたなら本望だ。。。』
世の中で、こう考えている人。。。どのくらいいるんでしょうかね?
曲がりなりにも、信濃ワイナリーの営業職である私も、お勤めを終える頃にはこんな風に考えたりする心境になるんでしょうか。
【僕は見たんだよ。一番見たかった、信濃ワインにある1枚の絵を。。。
だから、だから僕は今凄~く幸せなんだよ。
疲れたろ…。僕も疲れたんだ。なんだかとても眠いんだ。】
パトラッシュ・・・。
って、これじゃ衰弱死、もしくは過労死じゃん。
冗談はさて置き、こちらの油絵は、平成11年5月に新社屋が完成した際にお祝いとして、とある女性の方から寄贈していただいたものです。
その方は、職業画家ではありませんが、長野県美術展(県展)などにも自筆の洋画を出品されておられる愛好家。
お名前は伏せさせていただきますが、そのダイナミックな作風は女性が描いたとは思えないくらい。大変、臨場感のある作品です。
この絵に隠された秘密って?
ミステリーっぽくなってまいりましたが、この写真。 このズームした部分が、今回の話のキモの部分なんです。
【判明したこと】
油絵に描かれた『赤く塗られた機械』は?
昭和三十年代に活躍した、葡萄の搾汁機でした。
厳密に言うと、コチラが初号機(エヴァンゲリオン風)。 絵の中のが同系の弐号機(シンクロしたよ、エヴァと)。
葡萄を房ごと投入し、アルキメディアン・スクリューと呼ばれる螺旋式のスクリューで、葡萄をシリンダー内へと送り込みます。
送り込まれた葡萄は、シリンダー内で押し付けられ、果汁は別に集約されます。
「スクリュー式」と業界的には呼ばれている、圧搾方式ですね。
フランス アンボワーズ ウィルメス社製。
最新設備の揃うワイナリーが居並ぶ中、もはや、「骨董品」の部類でしょうね、この搾汁機は。。。
アンボワーズ(Ambois)は、フランス中部、アンドル=エ=ロワール県のロワール川沿いにある絵のように美しい城下町。
1987年に、長野県諏訪市と姉妹都市になっていました!! へ~。
ただ、コイツを見てると、私たちの諸先輩方の「汗」「涙」、そして「情熱」を感じずにはいられません。
2階に飾られた油絵よろしく、無名の画伯が描いた情熱は、時代の空気感を今なお私たちに伝えてくれています。

スズメヲウツノニタイホーヲモチダス ベルンハルト・ルジンブール
鉄という素材に魅せられた作者が、太い鉄骨や鉄板を自在に操り完成させた巨大な大砲は、1970年の大坂万博に出品されました。 遠くの山々にこだまする轟音が聞こえてきそうな迫力のある作品です。
(美ヶ原高原美術館 HPより)
「アモーレの鐘」で有名な美ヶ原高原美術館外に野外展示されている、有名な現代彫刻があります。弊社の搾汁機と何ら関連性はありませんが(苦笑)、野外に雨ざらしになっている環境下と、意匠が似ていると思いまして。。。
そもそも何故、この搾汁機は敷地内ながら、放置されているのでしょうか?
【判明したこと】
3階へ運べなかった。。。(重量過多のため)
信濃ワイナリーは、地上3階建て。 2階の「ワイナリーホール」は皆さまご存じの方も多かろうと思います。
以前、3階ではクラシックコンサートが催されたりしており、地域の文化的発信基地の意味合いを多分に含んだ「ホール」になるはずでした。。。
ただ、建設当初の「3階」の意義は、
「信濃ワイナリー 歴史展示ホール」の併設だったのです。
事実、長い歴史を彩る資料が、3階には厳重保管されています。 本来であれば、歴史の証人として3階まで運ばれる予定
であった搾汁機でしたが、理由は上記の通り。。。断念せざるを得ませんでした。
その代わりに、塩尻ワイナリーフェスタ開催を機に、年々増えるワイナリー訪問者の皆さま方へ、屋外展示というカタチで見て頂こう!(決して、放置ではないですね)とのことで、現在の位置に置かれたのでした。


インターネット上で調べると、同形機がフランスでは、「中古」としてフツーに売買の対象になっていました。
細かな部品調達が、現地では容易なのと、葡萄以外の果樹への流用(例えば、ノルマンディー地方のりんご)が当然の汎用機なのでしょうね。
売り手のアルフォンスさん。。。販売価格500ユーロって、どうなのよ? 安すぎない!?
ジャポンのsinano wineryにもあるからって、メールしてみようかな!?
あなたの知らない信濃ワイン Part1はコチラ
http://sinanowine.naganoblog.jp/e1083426.html
営業企画 橋詰